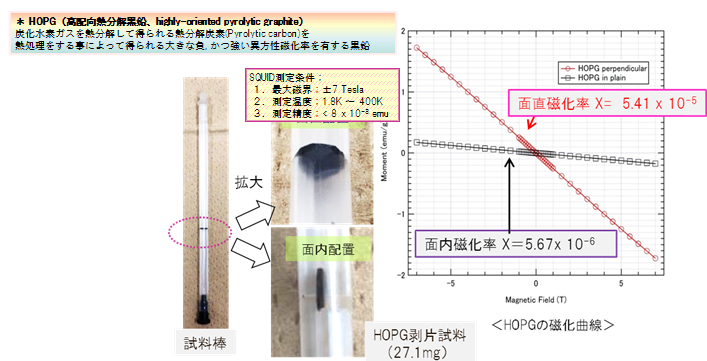弱磁性体や、反磁性体でも測定可能な高感度測定として
VSM(振動試料型磁束計)や、
SQUID 超伝導量子干渉素子測定を実施
目的・背景
◆ 従来、磁石材料や軟磁性体など、強磁性体材料を中心に、磁気特性評価をBHトレーサーや パルスBHトレーサーで行ってきた。
◆ 近年、弱磁性体の磁気特性、挙動を把握したいという顧客案件が増えてきており、新規に高感度受託測定を開始した。

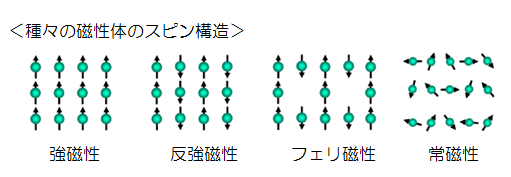
測定の特徴
1.温度可変対応型の振動試料型磁束計
(VSM; Vibrating Sample Magnetometer )
(VSM; Vibrating Sample Magnetometer )
<原理>
磁性体を一定の周波数、振幅で振動させ、電磁石側に取り付けたサーチコイルの出力を検出する。
出力をロックインアンプで増幅させているため、通常の強磁性体だけでなく、一部の反磁性や常磁性体の
弱い磁性体でも測定可能
<用途展開>
- ・低温(液体窒素温度)〜900℃までの連続磁気測定ができる。
- 「キュリー温度測定」、「磁気相転移温度測定」、「相同定」データ取得が可能
- ・電磁石は回転型⇒磁化特性の方位依存性、配向度が測定可
- ・測定可能な試料⇒粉末、薄膜、液体、バルク
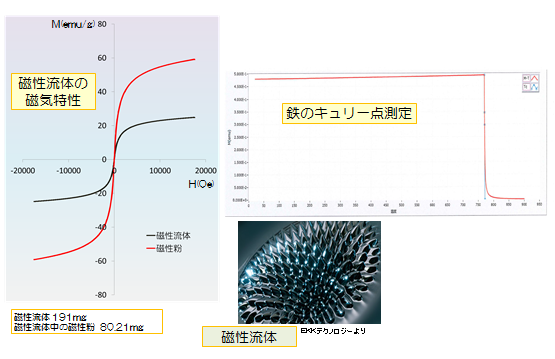
2.SQUID超伝導量子干渉素子
(SQUID;Superconducting Quantum Interference Devices)
(SQUID;Superconducting Quantum Interference Devices)
<原理>
超伝導状態のリングに外部から磁界を加えると、リングにはその磁界を打ち消すように電流(遮蔽電流)が流れる。
先に、リングの一部に細い部分(ジョゼフソン接合)を作っておくと、わずかな遮蔽電流が流れただけで超伝導の状態が崩れ、常伝導の状態となって、細い部分に電圧が生じる。
この原理を利用し、わずかな磁場の変化に対応して電圧を取り出すことが可能。
<用途展開>
「脳や心臓の神経細胞に発生する磁界を検出」できるほどの高感度な測定精度。
他の装置で計測不能な薄膜、反磁性体、などが計測可能。